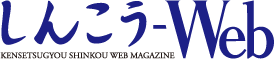はじめに
前回は木の国・石の国の建設材料について説明した。今回は楊重設備と都市や国の防衛の話をする。
2.楊重設備(クレーン等)の話

ローマ水道橋として有名なポン・デュ・ガール(図5)は、1世紀頃造られた、高さは約50m・延長500mの橋。最大6トン、2万個の石を積み上げている。石造構造物で大石を荷揚するには、クレーンが不可欠である。古代ローマや江戸でクレーンの使用状況は、どの様であったのだろうか。
レリーフ(図6)に示すように古代ローマ、またそれ以前にクレーンはあったのだ。現在と同じ動滑車と定滑車を多数、使っていたのである。一方、図7の法然上人絵伝(14世紀初頭)に見られるように、轆轤(ウインチのようなもの)はあったが、明治4年(1871年)の旧横須賀海軍工廠でのクレーンの使用が最初であり、江戸時代にはなかった。
古来、わが国では、石造構造物がほとんど造られなかったので、クレーンもコンクリートも不要であった。残念ではあるが、需要のない処に技術は発展しない、と言うことだ。


3.都市や国の防衛の話
江戸時代は城下町、古代ローマには城郭都市が多かった。都市や国の防衛が、構造物の造り方に影響を与えていたのかについて考えてみる。
兵隊の防備
図8の関ヶ原合戦絵巻と図9のローマ軍兵士の装備を見ていただきたい。日本では大将は、鎧・兜で十分の防備をしているが、兵隊は陣笠に槍や鉄砲・刀である。一方、ローマの兵士は顔面以外、被覆したヘルメットで覆っている。左手に楯、右手に槍や短剣。今でいう「半袖とスカート」は、軍団の後衛兵の装備。時代が1500年ほど違うので、当然、ローマ時代に鉄砲はない。
戦闘では、槍や矢は正面からばかり来るのではない。戦国時代、わが国では斜めや横、さらに後ろから銃弾・槍や矢が頭部を目がけて来ないと思っているようだ。「行け行け、どんどん。攻撃は最大の防御」と、自ら守ることは、不要との考えか、と思ってしまう。個人としての防御の甘さは、風土による、日本人の本質なのだろう。


都市の防衛
ローマのアウレリアヌス城壁(図10)と、1800年頃の東海道・高輪大木戸(図11)の絵図を見ていただきたい。アウレリアヌス城壁は帝国内の争乱や異民族の襲来により、3世紀後半に建設された。
全長19kmで、14k㎡の市域を取り囲んでいる。城壁は煉瓦被覆のコンクリート製で、厚さ3.5m、高さ8m。5世紀には高さを倍増させ、16mにする改修が行われた。侵入困難な城壁であり、住民の居住域を守っていた。
一方、現在も残る高輪大木戸は両脇に長さ9m、幅7.2m、高さ3mの石垣、その間に門(木戸)があり、簡単に侵入出来そうである。
江戸城天守の石垣は高さ13m。なかには丸亀城のように、22mにも及ぶ高石垣もあり、攻めるに難しい構造となっている。わが国の場合、城攻めは困難だが、城下町への侵入は容易である。しかし、日本の建設技術の素晴らしさを褒めたたえた宣教師フロイスは、厳しい見方もしている。
「たとえ関白の城(聚楽第)が、大砲を装備しない日本においては最も強固なものであるにしても、我らヨーロッパの城に比べるとはなはだ脆弱であり、大砲4門をもってすれば半日ですべてを破壊できるからである」と記している。まるで約30年後の大阪冬の陣での大砲攻めを予言しているようでもある。外敵の強さを知らないから無理からぬことなのだろう。
古代ローマと江戸では防備の考え方は全く違う。古代のペルシャ・ギリシャ・ローマ等は城郭都市。城壁外は蛮族や盗賊が横行して、安心して住めない。城郭攻略で火攻めは常套手段。逃げ場のない守備側をいぶり出したり、焼き殺したり、と。ただし燃やしてしまったら、財宝略奪はできなくなってしまうので、火攻めは最終手段であろうが。


マサダの攻城戦
攻城戦で最も壮絶と言われているのが、71年から73年のローマ軍とユダヤ軍のマサダの戦い。標高差130mを越える断崖上に千人超が守る要塞(図12)の攻防戦である。包囲されていても、水も数年分の食糧や武器の貯蔵があり、頂上部は農地となっていて長期籠城は可能だった。攻城戦では、断崖に約100万m3の盛土をして、斜度17度の侵入斜路を構築し、破城槌付き、高さ27mの鉄板被覆の攻城塔で攻め入った。
図13に示すローマ文明史博物館の攻城塔の模型から、推測すると、鉄板外装27mの高さだから、重量は100トンを超すであろう。
それを急勾配の登攀のみならず、100万m3の盛土作業も、頭上の敵要塞からの石や矢の攻撃にどのように耐えたのか、想像を絶する防御技術を持っていたのだろう。城壁破壊の前日、約千人のユダヤ人が集団自殺をしたのである。敗れれば、凌辱のうえ虐殺か奴隷かで、選択肢はなかったのであろう。
マサダの悲劇は今に伝えられ、イスラエル国防軍の入隊式は、その山頂の跡地で毎年行われている。2千年前の民族の悲劇を忘れるな、である。


ラキッシュの攻城戦

図14は紀元前701年の新アッシリアのユダヤ・ラキシュ攻略を描いたレリーフ。攻城塔は斜路を登り、城壁を破城槌で破壊。敵対者は、剥がされた生皮を串刺しにされ、晒しもの。「身の毛もよだつ」残虐行為が行われたのだ。
いずれにしろ攻城戦では、守備側は攻撃軍を撃退できなければ、死を覚悟しなければならない。
ともかく逃げ場がなかったのだ。そうとなれば必死になって、耐火性の高い石造城郭都市を造り、防御を固めざるをえないのである。
一方、我が国の場合、火攻めを多用したのは、合理主義者の織田信長ぐらいである。比叡山焼き討ち(1571年。1500人死亡)や長嶋一向一揆(1574年、約2万人火攻めで焼死)等である。火攻めを含めた過酷な攻城戦は少なかった。民族性のためであろう。
都市の守りかたの相違
城郭都市は防衛のためには、一定数以上の住民(戦闘要員)が不可欠である。人口が増えると、住居は高層化せざるを得ない。そうすると戦時の敵軍による放火や、平時の失火が心配となる。特に東方から攻めた古代ペルシャ軍は、現代の産油国出身。放火手段を沢山持っていたのだ。ともかく頑丈な耐火建築が求められた。したがってその城壁を作る技術者は尊敬されていたのだ。
一方、城壁のない江戸では、人口が増えると、江戸湾の埋立てを行ったり、荒野の開発を行ったり、平面的に広がった。さらに戦争の恐れは少ないので、火事になったら逃げだせばよいのである。
いずれにしろ古代ローマでは、兵士も都市も防御第一と、わが国とは大変違っていたのである。これは風土の影響であろう。 次回は「江戸とヨーロッパの都市の火災と防火対策」の違いを紹介する。