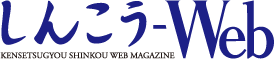2013.01.28
工種別技術史〜鉄筋コンクリート編
鉄筋コンクリートの歴史は、世界近代史の歴史といっても差し支えないだろう。世界各国のインフラ整備や社会基盤施設の建設において、鉄筋コンクリートに関連する技術ほど重要なものはないといって過言ではない。そこで、本稿では、「竹和会百年史 竹中工務店協力会の歴史」からの引用(一部抜粋)により、その歴史を振り返ってみたい。
-
[絵で見る江戸のくらし]
2017.03.15
文・絵=善養寺ススム
江戸城跡は現在の皇居ですが、天皇陛下がお住まいの場所は、当時、紅葉山や吹上と呼ばれた庭のような場所でございました。そして、江戸城の本丸や大奥、二の丸などがあった中心部は...続きを読む
-
[絵で見る江戸のくらし]
2017.02.23
文・絵=善養寺ススム
昨年の十二月に糸魚川市で起きた大火災は、江戸時代の大火を思わせ、大変驚きました。昔も今も人の力は、荒ぶる炎になかなか対抗できるものではないことを、改めて教えられました。...続きを読む
-
[絵で見る江戸のくらし]
2017.01.31
絵で見る江戸のくらし 20.竪穴式住居で日本建築について考える
文・絵=善養寺ススム
11月の終わりに、八ヶ岳を訪れまして、あるカフェの庭先に造られた竪穴式住居で囲炉裏にあたってきました。竪穴式住居は旧石器時代後期から平安時代まで、長い間用いられた日本の建築様式で、...続きを読む
-
[絵で見る江戸のくらし]
2016.11.29
文・絵=善養寺ススム
「伝統建築は釘を一切使わない」と、よく言われますが、平成25年に行われた伊勢神宮の「式年遷宮」には、なんと七万本近い釘が使われています。 ...続きを読む
-
[絵で見る江戸のくらし]
2016.10.31
文・絵=善養寺ススム
前回は工具のお話でしたが、今回はその材料、鉄のお話でございます。来年は日本史好きの人には大事な年、幕末維新(大政奉還)一五〇周年です。...続きを読む